~“共生”の原点とグローバルな視野を育んだ日々~
国連職員、小児科医、そして2025年には宝塚市長選にも挑戦することで話題の森臨太郎(もり りんたろう)さん。
そのグローバルな視点と、社会的弱者に寄り添うまなざしは、どこから生まれたのでしょうか?
今回は、森さんについて、たっぷり深掘りしてみたいと思います。
【森 臨太郎(もり りんたろう)さんの基本プロフィール】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 森 臨太郎(もり りんたろう) |
| 生年月日 | 1970年9月17日 |
| 年齢 | 54歳(2025年4月現在) |
| 出身地 | 兵庫県神戸市 |
■ 結婚相手はどんな人?
森さんの結婚相手について、公式なプロフィールや経歴の中では明確な記載はありません。ただし、いくつかの報道や関係者インタビューから見えてくるのは、
「国際的な活動に理解のあるパートナーがいる」
という点です。
森さんは、オーストラリア、イギリス、タイ、そして日本と、グローバルに拠点を移しながら活動してきた人物。これだけ多拠点での生活を長年支えてこられたということは、家庭内でのパートナーシップがしっかりしている証とも言えるでしょう。
また、2021年からの「タイ・バンコクと宝塚の二拠点生活」も家族と共に行っていたことが一部報道で触れられており、パートナーも一緒に生活の基盤を築いてきた可能性が高いです。
※現時点では、お名前やご職業などの詳細は一般公開されていません。プライバシーの観点からも、非公表を貫いているようです。
■ 子供はいるの?
こちらについても、森さん自身が積極的に“家族構成”を語ることは少なく、詳しい人数や年齢などは不明です。ただし、複数の大学で教育者としても活動している森さんは、子育てや次世代の教育に対する強い関心を持っており、その言葉の端々から、
「子育て経験者ではないか」
と感じさせるコメントも散見されます。
また、市長選出馬の際には、
「子どもや若者、高齢者、そしてヤングケアラーなど“声を上げにくい人たち”にこそ、政治は寄り添うべきだ」
と語っており、これは子育てを“当事者目線”で経験してきたからこその発言とも受け取れます。
■ 家族との時間をどう大切にしてきたのか?
森さんは、激務ともいえる国際機関での仕事や、研究活動に長く携わってきましたが、インタビューなどではしばしば、
「人の命や暮らしに携わるには、まず“自分の周囲の人”を大切にすることが第一歩」
と話しています。国連勤務時代も、家族との時間を工夫して持ちながら、地域コミュニティとのつながりを子どもと共に体験することを大切にしてきたようです。
タイや日本での生活の中では、学校や教育現場とも接点があり、家族ぐるみで“共生”のあり方を探っていた姿も見られます。
【小学校時代】武庫南小学校・鳴尾北小学校と“真木共働学舎”の夏
森臨太郎さんが生まれたのは、1970年9月17日。生まれ育ったのは兵庫県神戸市。出産は神戸市にある歴史ある病院「パルモア病院」だったとのこと。
小学生時代は、まず尼崎市立武庫南小学校に通っていました。ここは地元の公立小学校で、穏やかな住宅街の中にある学校です。森さんは3年生までこの学校で過ごしますが、その後、家族の転居に伴い、西宮市立鳴尾北小学校に転校します。4年生から卒業までを鳴尾北小学校で過ごすことになります。
彼の人生において、この小学生時代に訪れた**「真木共働学舎(長野県小谷村)」**での体験が非常に大きな意味を持っています。
共働学舎とは、障がいを持つ人々と健常者が共同生活を営む、自給自足を基本としたコミュニティ。森さんはここで夏休みを過ごし、土に触れながら生活をともにする中で、「社会的に弱い立場にある人々とどう共生していくか」という、人間としての根源的な問いに出会います。
農作業の手伝いや、障がい者の方との日常的なやりとりを通して、「支え合って生きること」の意味を、言葉ではなく体験として体に染み込ませていったのです。これが、後の彼の医師としてのスタンスや、政策立案における思想の“種”になったことは言うまでもありません。
【中学校時代】六甲学院中学校で芽生えた“知と精神の探究心”
小学校卒業後、森さんが進学したのは、六甲学院中学校。兵庫県神戸市灘区にある私立の男子校で、イエズス会によって設立されたキリスト教カトリック系の中高一貫校です。
この学校の特徴は、単に学力を育てるだけではなく、「人としてどう生きるか」を問いかけ続ける哲学的・精神的な教育に力を入れているところ。厳格な制服や礼拝などもあり、格式高い校風のなかで森さんは思春期を過ごしました。
中学時代の森さんは、クラスメートから見ても一目置かれる存在だったそう。勉強はもちろんのこと、読書家であり、歴史や社会、哲学にも関心がありました。放課後は生物部で昆虫採集や観察に熱中し、「自然の仕組みを知る」ことにワクワクしていたというエピソードも。
この頃すでに「医療か教育の道に進みたい」と語っていた森さん。家庭内でも「人の役に立つ仕事をしたい」と言っていたとのことで、思春期にしてすでに“使命感”のようなものを抱いていたことがうかがえます。
【高校時代】六甲学院高等学校で深化する「社会への問題意識」
そのまま内部進学で六甲学院高等学校に進学。中高一貫教育の利点を活かしながら、より深い学びに没頭していきます。
高校では、医療分野だけでなく、政治や国際関係にも興味を広げていったそうです。特に影響を受けたのは、倫理や宗教、そして社会福祉についての授業。カトリック教育の中で、「愛とは何か」「人が人として生きるとはどういうことか」といった問いに真正面から向き合う時間があったとのこと。
この時期の森さんは、生徒会活動にも関わり、ディスカッション形式の授業でリーダーシップを発揮。友人と社会問題について語り合う時間を何よりも大切にしていたそうです。
そして、高3の頃にはすでに「途上国の子どもたちに医療を届けたい」と口にしていたという証言も。大学進学を医師としての第一歩と捉えており、志望校を決める際には「地域医療」「国際協力」「小児医療」といったキーワードを大切にしていたといいます。
【大学時代】岡山大学医学部と阪神淡路大震災でのボランティア体験
1989年、森さんは岡山大学医学部に進学します。岡山大学は、地域医療に強く、実学主義を重んじる国立大学。ここでの6年間は、森さんにとって“実践と学問の融合”を深める濃密な時間になりました。
大学では、病院実習に積極的に取り組みながら、保健医療だけでなく公衆衛生にも関心を持つようになります。地域医療の現場に足を運び、患者さんの生活背景にまで寄り添おうとする姿勢は、当時の教授たちからも高く評価されていたそうです。
そして、忘れてはならないのが1995年の阪神淡路大震災。医学生だった森さんは、即座に現地入りし、神戸市長田区の保健所で医療ボランティアとして活動しました。
避難所での健康管理、感染症対策、メンタルケアなど、医療とは何か、人を支えるとは何かを肌で感じたこの体験は、彼の人生観を大きく変える契機となりました。
この経験を機に、森さんは「災害・貧困・差別と向き合う医療者になりたい」と強く感じたといいます。そして卒業後は大学院へ進み、1999年には医学博士号を取得。研究者としての道も歩み始めました。
◆医師としての第一歩:国内外で小児医療に従事
1995年から本格的な医師人生がスタート。淀川キリスト教病院、岡山大学病院、国立福山病院などで小児科医として研鑽を積みました。その後は、海外へ。
オーストラリア・アデレードの母子病院では新生児科の中級専門医として勤務。さらに、キャンベラ総合病院では上級医に昇進し、新生児医療の最前線に身を置きました。
小さな命と向き合い続ける中で、「個人の医療」だけでなく「社会全体の健康を守る」方向へと、森さんの視線は広がっていったのです。
◆大学院・国際機関での活躍:ロンドン→WHO→国連人口基金
さらなる学びを求めて、2004年には英ロンドン大学熱帯医学・公衆衛生学大学院で疫学修士課程を修了。ここで「科学的根拠に基づく保健政策(エビデンス・ベースト)」を本格的に学びました。
その後、WHO(世界保健機関)の本部にP-4テクニカルオフィサーとして勤務。さらに2018年からは国連人口基金(UNFPA)でアジア太平洋地域の少子高齢化政策を担当。タイ・バンコクを拠点に、国を超えて“人口と開発”というテーマに取り組みました。
◆教育者・研究者としての顔:大学での教鞭と論文発表
帰国後は、大阪大学大学院・医学系研究科にて「次のいのちを守る人材育成教育研究センター」の特任教授に。加えて、京都大学・関西学院大学などでも客員教授として教鞭を執り、学生たちに国際保健の最前線を伝えています。
また、論文発表は実に297本以上。著書も『イギリスの医療は問いかける』や『持続可能な医療を創る』など、政策提言型のものが多く、医療界からも高く評価されています。
◆宝塚市との関わり:地域医療から市長選へ
2021年、国連を退職して拠点を兵庫県宝塚市へ。地域医療に携わる一方で、地元の発達支援センターや子育て支援にも関わってきました。
そして2025年2月、「市民の暮らしにもっと寄り添いたい」という思いから宝塚市長選挙への立候補を表明。これまでの国際経験と医療の知見を、地域にどう還元できるのか?その挑戦が始まっています。
◆おわりに:森臨太郎という生き方が投げかけるもの
小児科医としての情熱、国際機関での冷静な視点、教育者としての熱意、そして地域での実直な姿勢。森臨太郎さんの歩みは、「ローカル」と「グローバル」を結ぶ“橋”のような存在です。
2025年の宝塚市長選に向けて、どんなビジョンを描いているのか?私たち一人ひとりが考えるヒントが、彼の人生の中に詰まっているように思います。
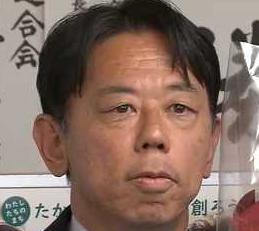
コメント